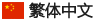用語解説
山口県立萩美術館・浦上記念館 学芸課長
石﨑泰之
| 用語 | 解説 | |
| 胎土 | たいど | 陶磁器の成形に適するように調整された粘土質の素地土のこと。成形後の器体の素地を指していう。 |
| 大道土 | だいどうつち | 「萩焼」の主要原土。防府市台道から山口市鋳銭司四辻の一帯で採掘される。可塑性が高く、鉄分も比較的少ないなど、素地土としては好適な条件を満たしている。茶碗などでは器面の表情といった、この土の装飾的効果がより重視された。坂古窯の初期では化粧掛けに用いられており、胎土(素地)としての資料は江戸中期以降の坂四号窯址から出土する。 |
| 金峯土 | みたけつち | 金峯山土とも表記される。大道土と混和して使用されるカオリン質の白色土。阿武郡福栄村福井下金峯で採掘される。素地土の粘性を抑え、耐火度を高めるために用いられる。 |
| 見島土 | みしまつち | 鉄分を多く含んだ赤黒色の土で、日本海上の萩市見島で採掘される。大道土と金峯土の素地土に混入、または化粧掛けとして用いられるが、「萩焼」の造形的表現には欠くことのできない原土である。 |
| 地土 | ぢつち | 窯元の近在にあって、素地土や化粧掛けに用いられる土の総称。坂古窯初期の出土資料では、鉄分の多い地土が胎土(素地)として用いられている。 |
| 水簸 | すいひ | 原土から素地土をつくる工程の一つで、土漉しともいう。水中に粉砕した原土を溶かし、一定時間滞留させるか、あるいは一定速度の流水を保持した状態で、粗い粒子や重い粒子を沈殿させ、求める粘土の泥漿を分離していく。この作業を繰り返すことで、粒径と比重が等しい素地土を得ることができる。 |
| 化粧掛け | けしょうがけ | 胎土(素地)に化粧土(エンゴーベ)で被膜をつくること。粗質胎土の表面を平滑に整えたり、吸水性を抑制するほかに、外観を白くみせたり、鮮やかな釉調を得るといった装飾性を求めて行われる。 |
| 化粧土 | けしょうつち | 胎土(素地)に薄く掛ける陶土の総称。塗り土とも、エンゴーベともいう。泥漿(スリップ)の状態のものも含めてよばれる。 |
| 泥漿 | でいしょう | 陶土と水を混和して濃密な液状にし、化粧掛けなどの装飾に用いる。スリップともよばれる。 |
| 釉 | ゆう | 焼成することによって、陶磁器の胎土(素地)の表面に、ガラス質の被膜をなすものの総称。「うわぐすり」と訓み、釉薬ともいう。 |
| 施釉 | せゆう | 本焼き焼成する前に、成形された器物の胎土(素地)へ、人工的に調合した釉をかけること。釉掛けともいう。方法としては「ずぶ掛け」「柄杓掛け」やコンプレッサーによる吹き付けなどがある。 |
| 釉調 | ゆうちょう | 施釉して焼成された器物の、表面の状態をいう言葉。主に釉面の質感や視覚的効果から得られる美感を対象として用いられる。 |
| 土灰釉 | どばいゆう | 雑木(マツ、クヌギ、ナラ、イスなど)を竈などで燃やした灰を媒溶剤に用いた透明釉。木灰釉ともいう。「萩焼」の場合、長石との調合比率は、柄杓合わせで五対五が一般的だが、製作目的に合わせて調整がされる。 |
| 長石釉 | ちょうせきゆう | 温かみのある乳白色の釉。萩の場合、単味で使用されることはほとんどなく、長石十に対して土灰が二~五の割合で混和される。かつて、原料の長石は防府市牟礼産の浮野長石や萩市小畑産の長石が使われたという。 |
| 藁灰釉 | わらばいゆう | 土灰釉に藁灰を調合した失透性の白濁釉で、「萩焼」を代表的する釉の一つ。白萩釉、白釉、藁白ともよばれる。萩のほか、唐津をはじめ上野、高取、薩摩など、16世紀末から17世紀初頭にはじまったとされる朝鮮系西日本諸窯を特徴付ける釉である。そのため、朝鮮半島から移入された技術と考えられてきたが、韓国南部諸窯址からの明確な資料はない。近年は、中国の福建省や広東省の民窯の技法との関わりを指摘する見方もある。 |
| 休雪白 | きゅうせつじろ | 三輪窯十代休雪(休和)と十一代休雪(壽雪)の兄弟が、藁灰釉を改良して開発した釉。厚みのある、失透性の純白色の釉調を特徴とする。 |
| 貫入 | かんにゅう | 釉面にできた罅割れのこと。釉と胎土(素地)の熱膨張の差によっておこる。釉としては、欠点といえる現象だが、これを装飾的効果ととらえれば、鑑賞上のポイントとなる。 |
| 高台 | こうだい | 器物の底部にある台のこと。器体底部を削り出して成形した削り高台と、別に粘土を成形して器体に貼り付けた付け高台とに大別される。『隔蓂記』正保四年(1647)正月21日の条の「茶碗 割香台之高麗」とある「香台」が高台という名称の初見例とされる。 |
| 畳付 | たたみつき | 器物の底部のことで、直に畳に接する部分を指していう。本来は、糸切りや板起こしの底をもつ、茶入や水指の見所として用いられたが、茶碗などの高台底部についてもいわれるようになった。 |
| 見込み | みこみ | 碗・皿・鉢などの口が大きく開いた形の器の内面をいう。とくにその中央部を指してよぶことが多い。 |
| 目痕 | めあと | 施釉陶器を焼成するときに、釉の熔着や器底の垂れ下がりを防いだりする支持物を目といい、その痕跡を目痕という。「萩焼」の目には胎土や砂のほか、アサリなどの二枚貝の殻が用いられる。 |
| 土味 | つちあじ | 茶入や茶碗などの釉掛けされていない露胎部の土の表情をいうときに用いられる語。 |
| 高麗茶碗 | こうらいちゃわん | 朝鮮半島から輸入された茶碗の総称で、ほとんどは朝鮮時代の初期から中期までの製作である。茶会記での初見は『松屋会記』天文六年(1537)とされる。高麗茶碗は、日用雑器の碗が茶人によって見立てられて茶碗となったものと、日本からの注文によってつくられた茶碗に大別される。その作行は細かく分類され、各種名称が与えられている。 |
| (釉の)ほつれ ちぢれ |
胎土(素地)と釉の熱収縮に差ができて、胎土上に釉の乗らない部分のできること。この現象は、釉めくれともいわれる。そのほかに、梅花皮とよばれる鉋削りの痕で、皺状になった胎土上に現れるものもいう。いずれも釉の一種の欠点ではあるが、これを景色とみて鑑賞対象とされることが多い。 | |
| 小畑陶磁器 | おばたとうじき | 江戸時代後期から大正・昭和初期にかけて、「萩焼」にも使われる小畑土を利用し、萩市椿東小畑地区で焼造された陶磁器。文化11年(1814)に山城屋文蔵・孫四郎父子によって興された日用食器類生産の窯をはじめとする。磁器を主力製品としたが、やがて肥前磁器の流通拡大に押されるかたちで、廃窯あるいは「萩焼」製作へと転換していった。 |
| 御用窯 | ごようがま | 「萩焼」の場合、松本の御用窯は藩窯という位置付けであり、陶家は禄を受け、窯場の営繕や生産資材、人夫などはすべて藩が賄った。一方、深川は一時期御用窯としてあったが、同時に自分焼という商品生産を認められており、純然たる御用窯とは言い難い。藩窯の経営は、松本の古窯址で茶陶とともに日用器が大量に出土していることから、日常は領内の需要に応じた日用器を生産し、藩主または藩から命を受けたときに茶陶を製作するものであったと推測される。 |
| 三島手 | みしまで | 灰色の胎土に白土象嵌などで装飾が施された炻器のこと。高麗青磁の末裔的性格を持つもので、朝鮮時代前期を代表する陶磁器。粉粧灰青沙器、またはこれを略して粉青沙器、粉青などともよばれる。 |
| 台柄 | だいがら | 本来は籾から玄米に脱穀するための農具。藁灰を粉砕するために用いられた。 |
| 鬼萩手 | おにはぎで | 粗い砂目の素地土でつくられた「萩焼」。この素地土は、水簸して得られた精緻な土質に、粗砂を練り混ぜて得られる。精細な素地土だけでつくったものを「姫萩手」ともよぶ。 |
| 水挽き成形 | みずびきせいけい | 轆轤成形の際に、水を用いて素地土を挽き上げる方法。手捻りや型打ちなど、轆轤を用いない他の方法と区別してよばれる。 |
| チリメン皺 | ちりめんじわ | 陶器や炻器にみられる縮緬のような細かいささくれ状の皺のこと。仕上げの際に、鉋で胎土を削ることによって生じる。胎土の乾燥程度や土質の精粗、轆轤回転の速度なども関係する。 |
| 割高台 | わりこうだい | 高台を一カ所から四カ所程度欠き割ったものの総称として用いられ、切高台ともいわれる。また、高麗茶碗の割高台を指しており、高橋箒庵編集の『大正名器鑑』には九碗があげられている。それらは、①高台内部を削らずに十文字の切り込みを入れて分割したもの五碗、②高台内部を削って輪高台として三カ所を切り取ったもの三碗、③高台の四カ所に切り込みを入れて(焼成後に)高台畳付を十文字状に彫ったものといわれる一碗である。①~③の形状にはそれぞれ特徴が認められ、同一概念とするには曖昧さが残る。狭義的概念としては、割高台を①の「十文字」ともよばれる形状の高台とみるのが適当ではないだろうか。 |
| 切高台 | きりこうだい | 広い意味では割高台と同義に使われるが、輪高台の一~四カ所を篦で切った形状の高台をいうのが適当と考える。 |
| 桜高台 | さくらこうだい | 割高台の一種ともみられる。高台の外側から切り込みを入れ、高台内部を削ってから、指で押して花弁状につくった高台。花高台ともよばれる。 |
| 輪高台 | わこうだい | 器物の底部の輪状の高台。轆轤を使用し、あるいは使用せずに内部を削ったものと、粘土紐を貼り付けたものがある。 |
| 竹節高台 | たけのふしこうだい | 高台の外観に竹の節のような形状をみせるもの。祖形は高麗茶碗の井戸に求められる。 |
| 白泥 | はくでい | 白色の泥漿のこと。化粧掛けに用いられる。 |
| サヤ(匣鉢) | 窯道具の一種で、陶磁器を焼成する際に用いる容器。耐火度の高い粘土で作られている。匣鉢に入れられた器物は、降灰などの不純物の付着や、炎が直接にあたることから保護される。 | |
| 古萩 | こはぎ | 『本朝陶器攷証』には「古萩と云うハ初代より三代頃を云伝へ申候」とあるが、伝世品と出土資料において、初代坂髙麗左衛門から三代坂新兵衛までの作例とその他の作例を、実証的に比定することは難しい。今日では広く江戸時代につくられた「萩焼」の総称として用いられている。 |
| 枇杷釉調 | びわゆうちょう | 透明釉をいわゆる酸化炎で焼成すると、胎土と釉が反応して淡黄色に明るく発色する。茶碗の場合、枇杷の色に似ているところからこれを枇杷釉調と称する。 |
| 攻め焚き | せめだき | 焼成の段階で、器物の釉が熔けてから、大量の薪を短時間のうちに投入して、窯の中の雰囲気を還元状態にすること。 |