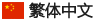萩陶芸の現在――
あるいは「萩焼」の今日性
山口県立萩美術館・浦上記念館 学芸課長
石﨑泰之
はじめに
「一楽、二萩、三唐津」と謳われ、茶の湯の具足としての茶碗にひときわ声価の高い「萩焼」は、中国地方に一大勢力を誇った戦国大名の毛利氏が、近世初頭の慶長九年(1604)に萩へ移ったのちに、萩藩の御用窯として開窯されたのをはじまりとします。
その発祥と展開については、いつの頃より用いられたのか詳らかではない前の格付けが示すように、優れた茶陶を生み出した窯業地としてのイメージを反映して、中世末期以降に流行した茶の湯との関わりのなかで語られることの方が多いようです。実際に伝世する「萩焼」茶碗の造形には、普段づかいの雑器でありながらも侘びた風情の感じられる朝鮮産の施釉陶器を高麗茶碗と称して賞翫した、茶の湯の世界の鑑賞眼に通底する独特の美感が濃厚に映し出されているからでしょう。
ただし、このような優れた茶陶を生み出した「萩焼」というイメージは、古窯や消費地遺跡などでの考古学的発掘調査の成果を受けて、近年しだいに修正が加えられてきています。江戸前期の作陶活動の状況が窺える萩市松本や長門市深川の古窯址からの出土資料には、碗、皿、盤、鉢などじつにバラエティーに富んだ器種がみられ、しかも日用とおもわれる粗製品が多数を占めるなど、従来「萩焼」を特徴づけてきた抹茶茶碗をはじめとする趣味性の高い茶陶の割合は意外に少なかったことがわかってきました。今日では「萩焼」の発祥つまり毛利氏の御用窯開窯の事情は、17世紀初め頃の西日本における施釉陶磁器に対する需要の増大が背景にあったと考えられています。
それでは前のような、茶陶を生産品の代表とみる「萩焼」のイメージは、いつ頃から定着してきたのでしょうか。そしてこのイメージは、同時代の陶芸という視座から眺めたとき、この地域の作陶活動の現在にどのように反映し、またどのような方向性を暗示し得るものなのでしょうか。こういった「萩焼」の今日性の問題について考えていく前に、ひとまず近世におけるこの地域の作陶活動の歴史を概観してみましょう。
朝鮮渡来の陶工
織田、豊臣両氏による全国統一の過程で政治的な安定をみせはじめた16世紀後半の社会では人々の経済力もしだいに向上し、華やかな青花磁器を主流とする中国や朝鮮からの輸入陶磁器や、中世以来国産の高級施釉陶器を焼いた瀬戸・美濃窯の製品の供給量を上回る需要状況が現れます。しかし、西日本地域には1560年代にはじまった北部九州の唐津焼以外に施釉陶器を生産する窯はありませんでした。このように滑らかな釉薬が掛けられた比較的堅牢な施釉陶器に対する需要が高まっていたとき、豊臣秀吉最晩年の文禄・慶長の役(1592〜98)で朝鮮半島に出陣を命じられた西国大名のうち力のある者たちは、当地で技術をもった陶工たちを確保して連れ帰る機会を得たのです。これは萩とほぼ同じ頃に開窯した施釉陶器窯の上野、高取、薩摩などにも共通する事情で、有田を中心とする肥前地方で興ったわが国最初の磁器生産も含め、今から四百年ほど前に山口・九州の各地に相次いで窯場が築かれたのは時代の要請であったといえるでしょう。
文禄・慶長の役とよばれる朝鮮半島のほぼ全域でおこなわれた約七年間の軍事行動は、彼我に多大な犠牲を強いたばかりで所期の戦争目的は果たされずに潰えてしまい、大量の朝鮮人連行とその結果振興が図られた各種産業、とりわけ目立った成果としての製陶産業の拡大ゆえに、後世「ちゃわん戦争」とか「やきもの戦争」とよばれもしました。前掲の諸窯はいずれもこれに出陣した西国大名が彼の地より連れ帰った李朝(1392年〜1910年、国号は朝鮮)の陶工によって開窯されたという点に共通性があり、「萩焼」の場合には李勺光と李敬という名の朝鮮渡来の兄弟陶工がその開祖とされています。
近世における作陶活動の展開
「萩焼」の発祥とその後の展開について、その史料的根拠とされる文献の第一は、毛利家文庫の史料のひとつで毛利家家臣が藩に提出した自家の系図や略歴をまとめた『譜録』のなかに収められている御用窯各家の『略系並伝書』です。ただし、そのうちの山村家文書が五代源次郎により明和四年(1767)、坂家文書は五代助八によって明和二年(1765)、三輪家文書は五代十蔵が明和三年(1766)、佐伯家文書は三代半六が寛保元年(1741)といった時期に提出されたもので、これら文献史料の記述はいずれも萩藩成立から150年ほど下った頃のものです。そのほかに、藩士の俸禄を記載した『分限帳』『無給帳』にある陶工名の記載を加えて検討がなされていますが、これらの文献の記述にはいくつかの矛盾や不可解な箇所も存在します。詳細は末尾に掲げた参考図書をご覧いただくことにして、それらのなかでもっとも信頼できるとみられる、李勺光の流れを引く山村家の文書を軸に、江戸期における作陶活動の態様をおおまかに整理してみました。
①松本焼・窯薪山御用焼物所
萩藩御用窯の創窯は、豊臣秀吉から中国八カ国120万石の支配を安堵された天正19年(1591)に、本拠を郡山城(広島県高田郡吉田町)から広島城に移した毛利輝元が、翌文禄元年(1592)には秀吉の出征命令に従って兵三万人とともに渡海し、その夏の終わり頃から慶尚道開寧に在陣したことにその端緒をみることができます。その年の晩冬、秀吉朱印状にて朝鮮の技芸ある陶工を招致するようにとの指令を受けた輝元は、翌春には病気養生のために当時養嗣子であった秀元と交代して釜山へ退き、さらに秋の気配を感じる頃に重ねて帰国を命じられていますので、おそらくその頃に朝鮮人陶工を連れ帰ったものと考えてよいでしょう。
今日「萩焼」開祖とされる李勺光は、輝元が陣を構えていた朝鮮のどこかで弟とともに認められていたのでしょう。秀吉の命によって文禄の役の際に連れてこられ、大坂に住まわされていましたが、のちに輝元に預けられたそうです。秀吉の没する以前のことですから、居城建設中の広島に李勺光は移されたのでしょうか。「高麗焼物細工累代家伝」の秘法に長じた陶工であった李勺光は、慶長五年(1600)の関ヶ原の合戦に敗れた輝元が萩に移った慶長九年(1604)頃、弟子たちとともに従って萩城下の東郊松本村中ノ倉御用窯を開いたとされています。そして、どのくらい後の頃かわかりませんが、その弟も萩に招かれて高麗焼物細工を仰せつけられ坂本助八(のちに坂と改姓)と名乗ったようです。
その後の李勺光の消息については記載もなくその卒年ですらわかりませんが、ただ一人の男子があって、他界した父に代わって叔父の坂助八が養育したとされています。この子は元服して山村新兵衛光政と名乗り、父と同じ五人扶持切銭銀弐百五拾目という厚遇に処せられ、寛永二年(1625)には「作之允」を任ぜられて松本窯薪山御用焼物所の惣都合として焼物師達を統括しています。同じ時期には弟の坂助八も「髙麗左衛門」に任ぜられ、三人扶持切米七石六斗をあてがわれたとあります。
のちに藩士との喧嘩沙汰で相手を殺めた山村新兵衛光政は、隠居させられて松庵と号し、萩城下の古萩に屋敷を遷されていますが、中級藩士並みの銀子の切銭で処遇されるなど、その家格は弟の坂助八が李勺光の弟子筋とほぼ同様の切米で処遇されているのと比べ、格別な扱いであったことがわかります。
②深川焼・三ノ瀬焼物所
山村松庵(新兵衛光政、作之允)は、明暦四年(1658)に先に殺めた藩士の子と弟の仇討ちに遭ってその生涯を閉じることになりますが、それ以前の承応二年(1653)には松庵の弟子筋の蔵崎五郎左衛門と同族の勘兵衛が、また明暦三年(1657)には同じく弟子筋に当たる赤川助左衛門(のちの田原家)、赤川助右衛門(のちの新庄家)の一族が、それぞれ独立開窯を許されて大津郡深川(現長門市湯本)の三ノ瀬に移住し、地下の住人九郎右衛門(のちの坂倉家・坂田家系)と協力しあって、大寧寺の山林を薪山として拝領し窯を築いています。ただしその窯は、松本御用窯と同じく藩庁御蔵元の支配下におかれてはいましたが、藩の御用以外に「自分焼」と称される商いをも許されるという経営形態のものでした。山村松庵の子息平四郎光俊は、父同様の処遇を受けて「三ノ瀬焼物所惣都合〆」を命じられており、ここで萩・松本の御用窯における李勺光の系統はすべて深川に移ってしまいました。
この深川の窯は元禄六年(1693)になると、山村家のみは藩の御細工人の身分を保たれながらも、地下支配(庄屋支配)に移管されて御用窯ではなくなります。しかし18世紀には赤川一族が東ノ新窯の増築をおこなうなど、深川三ノ瀬における民窯は旺盛な生産力を発揮しています。近年の江戸をはじめとする都市遺跡における考古学発掘調査によっても、この時期の深川焼の碗、鉢、向付といった資料の出土が認められていますので、その繁栄ぶりは想像に難くありません。そういったなかで、御細工人の山村家では五代源次郎光長服喪中の安永三年(1774)、その養子源右衛門が刃傷沙汰をおこし、それによって家禄没収、御家断絶となり、「萩焼」開祖とされる李勺光以来の家系は潰えてしまうという事態となりました。その後は赤川喜右衛門、坂倉萬介が御細工人に取立てられ、さらに坂倉善右衛門、嘉助と続きますが、藩直轄の御用窯への復帰はありませんでした。
③松本御用窯の拡充
山村家およびその弟子筋の深川移住後の明暦三年以降において、松本の御用窯は坂家を中心とした運営がなされていたとおもわれます。寛文三年(1663)には新たに三輪休雪(初代)と佐伯実清(初代半六)を御雇細工人として召し抱え、松本における生産体制の強化が図られます。三輪窯はこのころ前小畑小丸山にあり、佐伯家は無田原に窯を築いていましたが、初代佐伯半六の死を契機にその窯を継ぐことになった三輪家が無田原に移って現在に至り、佐伯家は初代半六の子義勝の成長を待って大釜という場所で新たに窯を築きます。のちに佐伯窯は、深川の赤川助右衛門系から迎えた養子の三代半六のとき、先祖の姓である林に改め、歴代半六を名乗って仕えていましたが、名工といわれた六代半六(林弥十郎、泥平)の息子が出奔したことによって、文化14年(1817)には家禄没収に処され断絶してしまいます。
こういった、松本御用窯における新たな展開のなかで注目されることは、元禄13年(1700)に、初代三輪休雪が齢70にして楽焼修業の藩命を受けて上洛し、楽焼を習得して戻って来ていることです。このことは、これまで朝鮮系の施釉陶器生産を指向していた萩藩の御用窯経営方針に転機がおとずれたことを意味するもので、いわばこの地域の作陶が和物茶碗の造形を一段と意識するようになり、置物づくりを含めて、新たな方向へと歩み始めたことを示しています。三輪窯ではその後四代休雪もまた楽焼の修業を命ぜられており、代々楽焼を御家芸としていたことがうかがわれます。
このころの松本御用窯生産品の用途について、茶陶との関わりで興味深い史料が残っています。『諸觸書跋』所収の元文四年(1739)藩庁からの通達に「今後は御遣物をする際は充分に検討した上で使うよう」とあり、江戸において将軍家はじめ幕閣、諸大名に対して、御用窯生産の茶碗などを「御遣物」として国元から送らせていたことと、それが不足気味であったことが推測されます。また、江戸中期にあたるこの時期には、文人趣味の煎茶が流行していたことから、御用窯への製作指示にも「御せんじ茶々わん」が現れてくるようになります。
④小畑陶磁器の勃興と衰退
江戸後期の19世紀になると萩城下からやや離れた小畑の地に陶磁器窯が興りました。小畑はもともと良質の陶土や磁質の土がとれる場所で、御用窯となる以前の三輪窯もこの辺りに窯を築いていたところです。松本御用窯においても、茶碗などの茶道具類には瀬戸内沿岸の防府で採れる大道土をわざわざ運んで用いていましたが、花入や置物の製作には小畑の土を使っていました。また松本御用窯の陶器製作は藩の管理下におこなわれて、生産量もあまり多くなかったとみえ、民間での用途の多い飯碗、土鍋、土瓶などの日用器類は京焼や信楽焼といった他国の大窯業地からの移入陶磁器にたよっていたようです。そこで文化11年(1814)には、すでに隠居していた六代林泥平(林弥十郎)を頭取として、上方から絵付職人を招き、小畑の原土を使った陶器をつくる西山窯が浦小畑に開窯されました。これは萩藩の御用商人山城屋文蔵とその子孫四郎の経営によるものでしたが、一時は藩の御産物方の支配下に置かれたこともありました。こういった動きは、江戸中期から後期にかけて全国の諸藩においておこなわれた殖産興業策としての窯業振興が背景にあります。ただし、民間によるこの事業は、前述の林家の断絶によって頭取林弥十郎(六代半六、泥平のちに古林仕平)が去り、一時頓挫を余儀なくされたようです。ちなみに、この古林仕平(泥平)は陶技にすぐれた名工であったらしく、小畑の後には深川、皿山(下関市長府)、大島や見島(ともに萩市沖)を渡り歩いた後の文政11年(1828)には赦されて小畑の永久山窯に戻ってきています。
文政六年(1823)には白磁器の焼造を見るに至り、小畑には先の西山、永久山をはじめ寿九山、天寵山、泉流山、素玉山、大向山といった七つの窯が磁器生産をおこなうようになりました。これらの窯による製品が萩藩内外のどの程度の範囲に流通していたかどうか詳細はわかりませんが、伝世するものや萩市内の町屋址からの出土資料にもこれらが少なからずみられるところから、陶磁器に対する一般の需要を満たし、人々の生活をより一層幅のある豊かなものとしていたことは間違いないでしょう。やがて、幕末維新の混乱の中で経済的裏付けを失い、廃業もしくは陶器窯への転向を余儀なくされ、小畑における白磁器の生産は衰退してしまいます。
一方、茶陶においては民間にもその需要が増したとおもわれ、それに関連した興味深い萩藩の布達がみられます。藩庁は文化12年(1815)と天保三年(1832)の二度にわたって、松本焼の「濃茶々碗」に紛らわしい茶碗の製造と御用窯以外での「大道土」使用の禁令を出しています。このことは、茶陶に関しては当初から藩が独占的経営によって厳しく管理されるべき政策を取っていたことを裏付けるとともに、幕末にもなるとその統制さえままならない状況となってきたことがうかがえる貴重な事柄といえるでしょう。以上が近世における作陶活動の概観です。
「萩焼」の成立―近代の茶の湯のなかで
明治維新の変革はこの地域の作陶活動にも大きな変動を与えました。とくに松本の各窯はこれまでの藩営から独立自営への転換を余儀なくされ、一挙に経済的裏付けはおろかその存立さえ危うい状況となってしまいます。多くの陶工や職人が離れていくなかで、松本や深川などの各窯元が、この近代化の荒波のなかを自営販売の開拓に活路を求めたのが明治における状況でした。こういったなかで注目される出来事としては、明治十年(1877)に始まった「内国勧業博覧会」と明治33年(1900)にパリで開催された「万国博覧会」に代表される各種展覧会への「萩焼」の出品が挙げられます。これによって「萩焼」は一時的ではあれ、販路拡大の方途を見出していったのでした。しかし、鉄道などの近代的交通網の充実に伴う 流 通機構の改革は、有田や瀬戸などの大窯業地の製品が質や価格において広範な地域への供給力を増し、幕末の混乱期を乗り切って明治初期には一時繁栄のみられた小畑や深川の各窯もしだいに衰退へと向かいました。さらに近代的設備を整えた工場で酒瓶や薬品容器などのガラス製品の生産もはじまり、陶磁器自体の需要が希薄になって窯業全体が苦境の時代を迎えることになります。ただこういったなかでも、萩松本の名工大和作太郎(松緑)が明治25年(1892)に山口の宮野に松緑窯を開窯し、「山口萩焼」(宮野焼)を興していることは、この時期の作陶環境にまったく発展の余地が残されていなかったわけではなかったといえるでしょう。ただし、つづく大正期、昭和初期と、工場での大量生産と広範な販売網を有する大窯業地に互することのできなかった、この地域の作陶環境は常に厳しく、慢性的な不況体質に陥っていたといえるでしょう。
そのような状況のなかで、他の大窯業地にはない非常に特化した商品の製造に意を尽くしたのがこの頃でした。この地域が萩藩御用窯の時代から連綿と作り続けてきた茶の湯の道具、すなわち茶陶への回帰が模索されるようになってきたのです。折しも明治後期からの時代精神がナショナルな思想と感性によって主導され、日本文化の伝統的なものを尊重しようとする風潮が台頭してきた時期で、茶の湯がふたたびブームとなった頃に重なります。前の各種博覧会への「萩焼」の積極的な出展活動につづくように、大正期になると一層の盛り上がりをみせた茶の湯の世界に「萩焼」の茶碗の存在が認められるようになりました。とくに十二代坂倉新兵衛は「萩焼」をより品格の高いものとするため表千家に入門し、家元伝来の茶碗を学び写すことと、それらの茶陶を積極的な個展活動によって売り出し、「茶陶萩」のブランドイメージづくりに努めたことが知られています。冒頭に挙げた「一楽、二萩、三唐津」の品等は、じつはこの頃にできたのではないかとおもわれるほど、「萩焼」イメージは茶の湯の世界に浸透していきます。
伝統美を求めて
明治40年(1907)にはじまった「文部省美術展覧会(文展)」はわが国最初の官設展覧会ですが、これは日本画、洋画、彫刻の三部門のみの公募で陶芸などの工芸部門は含まれていませんでした。工芸の分野の官製展覧会としては大正二年(1913)の「農商務省図案及応用作品展覧会(農展)」とこれにつづく大正13年(1922)の「商工省工芸展覧会(商工展)」があり、個人作家意識を持ち始めた大正期の工芸家たちはこれを主な活躍の場所としていました。やがて文展につづく官設展覧会である帝展の昭和二年(1927)第八回からは美術工芸の部門が新設され、また翌年には富本憲吉を中心に「国画創作協会(国画会)」の工芸部が設けられるなど、昭和初期は展覧会での発表を主に活動をする作家たちと、濱田庄司や河井寛次郎といったいわゆる民芸派の作家たちの大いに活躍する時代となっていました。
こういった工芸界の状況のなかにあって、これらの陶芸作家たちとは別の動きが生まれてきます。大正から昭和初期にかけて中国大陸の各地で主要な古窯址の発見が相次ぎますが、これに刺激され、古陶磁を愛好しつつ研究を重ね、その伝統美の世界を追求しようとした陶芸家たちの存在です。古陶磁の愛好と研究は作家ばかりでなく、学者や研究家、陶磁愛好家といった広がりを持っていましたが、陶芸家たちは身近な日本各地の古窯址と古窯採集の陶片にみられる古技法を探求することで、桃山茶陶にみられる造形的感覚を頂点とする伝統的な工芸美の世界に迫ろうとしました。そういったなかで美濃における荒川豊蔵、備前の金重陶陽などとともに、萩では十代三輪休雪(休和)が古萩の研究を進めるうちに藁灰釉に独自の改良を加え、「休雪白」とよばれる白釉を新たに「萩焼」の茶陶の伝統に加えたことは特筆すべきでしょう。
「萩焼」の今日性
近世初期にこの萩の地に定着をみた作陶の流れを振り返ったとき、今日広く認められるところの「萩焼」とは、じつは近代において成立した茶陶についてのイメージであったといってよいでしょう。ただし、こういった近代における「萩焼」概念成立の背景に、朝鮮半島から招来された製陶技術をもとにして、そのときどきの新たな造形的モードを取り込みつつ、風土に根ざした独自の美感を加えるという、この地域の作陶意識に絶え間のない新陳代謝があったことは間違いありません。それは前述のような出土資料や、今日眼にすることのできる伝世品の茶碗(古萩と呼ばれる江戸時代の茶碗)に、高麗茶碗、織部、楽などの素直な写しにはあり得ない、異質な造形要素が意図的に混入されていることからも容易に感得できます。萩の作陶には前近代から、先端的な表現をめざして挑戦するアヴァンギャルド(前衛)の造形思考が潜在していたように思えます。
20世紀に入った大正後半以降の近代的個人作家意識の昂りのなかで、わが国の作陶の方向性は大きな転換点をむかえました。「萩焼」においても産地の伝統的な素材や技術を拠り所としながら、作陶に個人的な造形表現を求める作家活動、つまり明確な芸術意識による創作活動としての陶芸が展開されます。これは作陶環境の条件整備的側面もありましたが、先ずなによりも「萩焼」の古技法を修得するうちに知覚し得た閾を超えようとする自己との壮絶な闘いがありました。陶工から陶芸作家へという作陶意識の転化、この超克こそが作り手をして自己の表現意欲を省察し、そして率直に造形として表出する方向へと醇化させていったのです。このことは、先述の三輪休和や吉賀大眉などわが国陶芸の20世紀を代表する作家たちや、そして現代陶芸の最高峰として斯界を牽引する三輪壽雪(十一代休雪)の造形に、その先進的作例として明確に現れています。
近代的な個人作家意識の形成と確立にその起点が求められるわが国の現代陶芸では、個人の自由な感覚によって導かれる造形性を重視した鑑賞的器であれ、東洋陶磁の技法を基礎として自己の創造性を発揮しようとした器であれ、実生活における機能性を重視しながら美感を与えようとした器であれ、そしてまた、造形の純粋性を問い続けて実用的な機能を排除する前衛陶芸とかオブジェ陶芸などとよばれる表現形式であろうとも、個人的作家意識を反映しない制作物=作品はあり得ないでしょう。素材・技術との不即不離の緊張関係を保ちながら、自己の表現を創造的に拓いていこうとする行為です。萩の陶芸の現在が、こういったわが国陶芸界の動きと軌を一にした作陶活動がなされていることはいうまでもありません。
前衛陶芸の分野で活躍してきた十二代三輪休雪(龍作)は、その襲名記者会見の際に次のように自身のこれからの制作を展望しています。「皆さんが伝統的だとおっしゃる父(三輪壽雪、十一代休雪、人間国宝)の仕事は私から見れば、革新的な感があります」「父の長い作陶生活における仕事は萩焼四百年のなかにどこにも出てこない」「茶陶であるから伝統で、オブジェであるから革新的ということではなく、それは茶陶の茶碗を作ろうが、どういう姿勢で作るかによって内容が決まってくるとおもいます」「私は父がやってきたように私も茶陶をやっても私なりの姿勢でやっていこうと思います」と。新たな表現領域の創出に挑戦し続ける豊かな感性こそ、この地域における作陶の栄えある伝統であり、萩の陶芸のこれからを拓く根源となるものでしょう。「萩焼」の今日性はここにこそあるのです。
参考図書
山本勉弥『萩の陶磁器』萩文化協会1950 (増補版森豊彦)1978
三輪休雪『日本のやきもの4』淡交新社1970
吉賀大眉『カラー日本のやきもの6』淡交社1974
河野良輔『世界陶磁全集7江戸(2)』小学館1980
河野良輔『日本陶磁大系14』平凡社1989
河野良輔・榎本徹監修図録『萩焼400年展―伝統と革新』朝日新聞社2001
石﨑泰之『窯別ガイド 日本のやきもの』淡交社2003